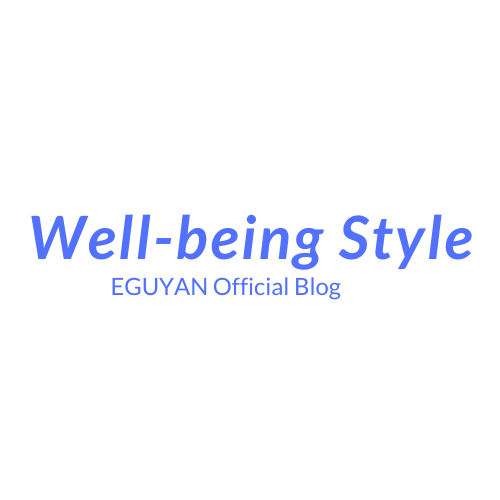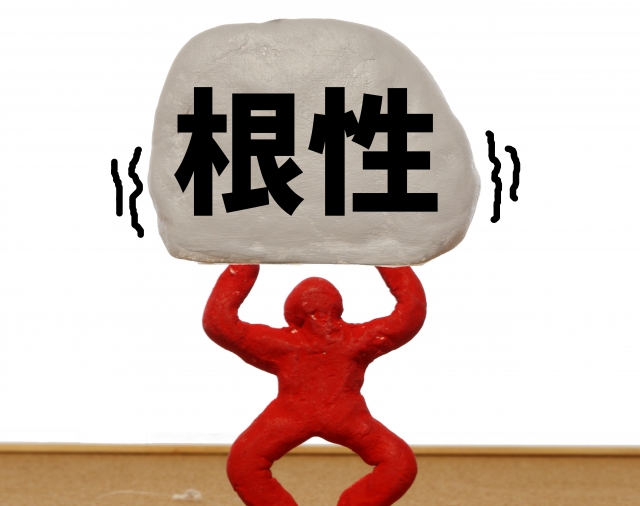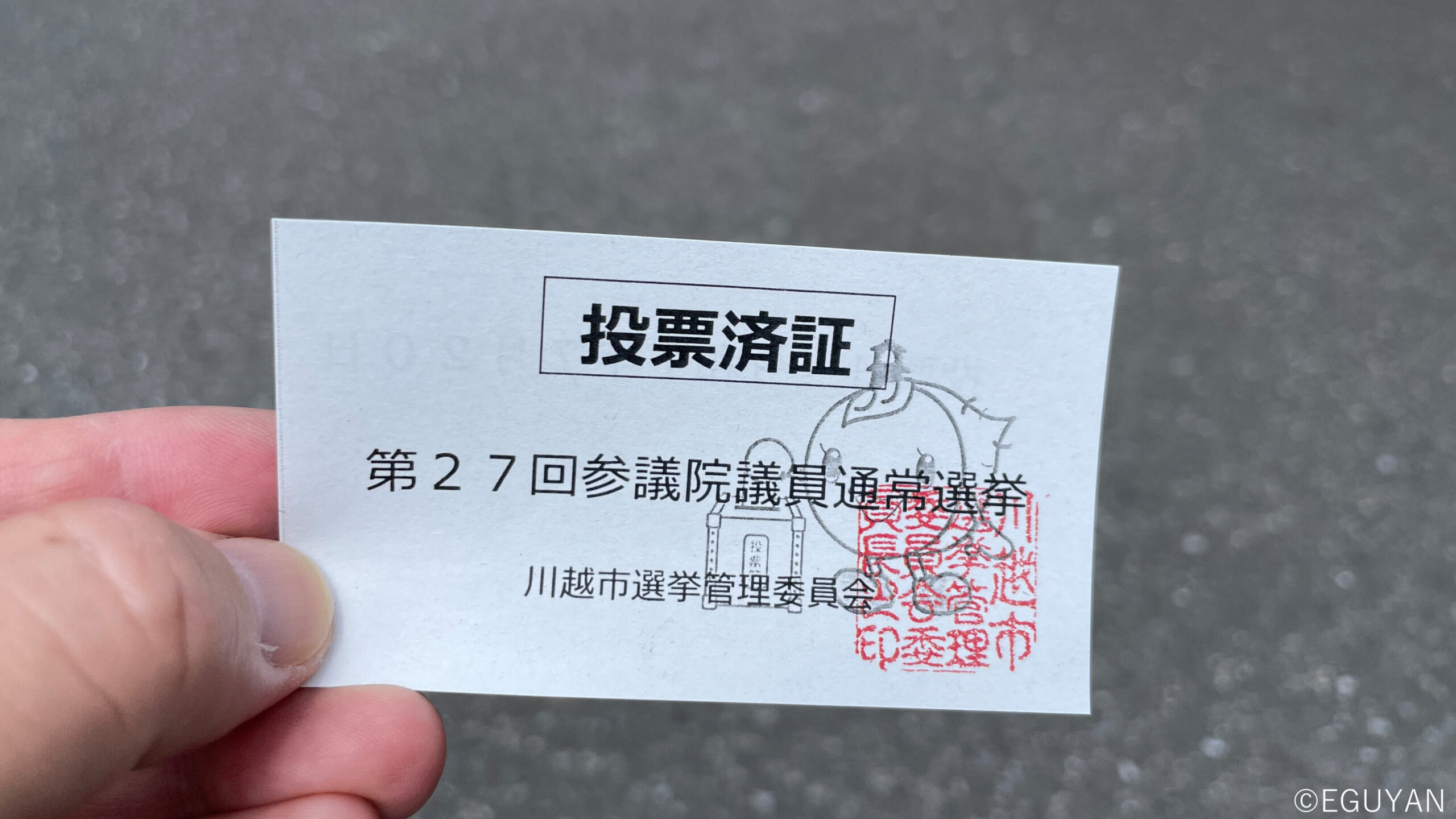タブーをタブー視しない。社会人が議論を避けないために必要なこと
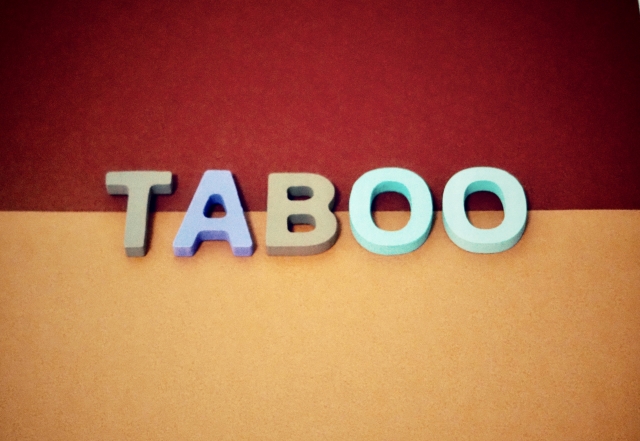
私たちの社会には、触れてはいけないとされてきたテーマが数多く存在します。
営業の場での野球や政治の話、学校での性教育、報道における暗黙の了解などです。
差し障りのない会話を優先する文化は、確かに摩擦を避けてきました。
しかし同時に、本来必要だった議論を遠ざけ、社会の停滞を招いてきました。
価値観の違いを尊重する働き方が社会を強くする
日本社会では「空気を読め」「みんな一緒でいい」という考え方が長く根付いてきました。
しかし、実際に人の価値観は多様です。
たとえばスポーツの話題。野球であれサッカーであれ、応援するチームが違えば意見は食い違います。
それでも、相手を尊重して語り合えば会話は理解を深める場になります。
職場でも同様に、違いを恐れず受け入れることが、強い組織を生み出します。
政治や性教育を語らない日本社会の課題
日本では政治の話題を避ける傾向が強くあります。
けれど、他国では市民が積極的に政治を語り合い、社会の改善に結びつけています。
日本で市民が政治談義を遠ざけてきたことは、政治の停滞を招く一因になっています。
性教育も同じです。
学校で十分に教えられなかったため、誤解や偏見を残し、性犯罪リスクを高めています。
さらに報道でも「触れないテーマ」が存在することで、誤解や無関心を生み、社会の議論を阻害しています。
タブーを避け続けること自体が課題を深刻化させてきたのです。
タブーの線引きを意識しつつ、建設的な議論を
もちろん、どこでも自由に語ればよいわけではありません。
採用面接での宗教・思想に関する発言は、差別や偏見につながる危険があり、厚生労働省も就職差別につながるおそれがあるとして禁止しています。
宗教や思想は自分がどう思うかは自由ですが、相手を批判したり押しつけたりすることは問題です。
政治に宗教団体が過度に関与することについても、憲法違反のリスクがあります。
これまでの日本は「言いたいことを我慢する時代」でした。
しかし今はSNSの普及によって、個人が意見を発信しやすくなっています。
次はビジネスの場においても、タブーに縛られず建設的に語り合う姿勢が求められます。
違いを尊重し合いながら意見を交わすことで、多様性は社会の力に変わります。
それが未来をより健全にしていく道だと思います。