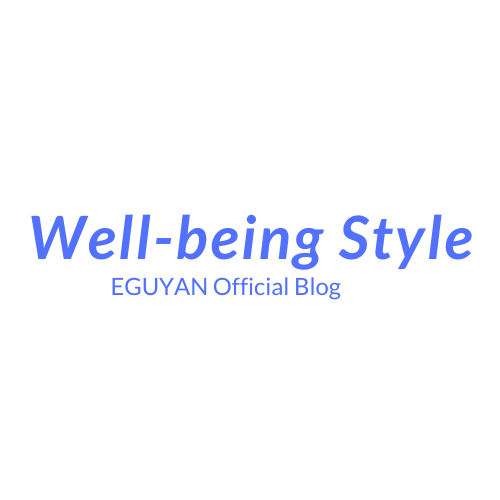一斉に休む時代は終わり?夏期休暇を“分散化”すべき理由

夏期休暇を一斉に取得する会社がいまだに多く存在します。
しかしこの時期は、公共交通機関や宿泊施設は混雑し、しかも高額な料金が発生します。
「みんな一緒にお盆休みを取る」という慣習に従い続ける必要があるのでしょうか。
混雑・高額・属人化…「一斉休暇」が引き起こす3つの問題
製造業をはじめ、いまだに「お盆週間は全社休業」というスタイルの会社も多くあります。
確かに長年の慣習ではありますが、それが招いている問題も少なくありません。
- 交通機関や宿泊施設の混雑
- 高騰する旅行・帰省コスト
- 業務の属人化による停滞
お盆期間はどこも混んでいて高い。それをみんなわかっていながら、毎年同じ時期に一斉に休む。
「取引先が休むから、うちも…」という流れに疑問を持ったことはありませんか?
すべての取引先が同時に休んでいるとは限りませんし、業務全体を止める必要があるのか、再考する価値はあります。
また、誰かがいないと業務が止まってしまう――これこそ、属人的な働き方の典型です。
属人的な働き方から脱却しよう
たとえば、ITトラブルが起きたのに唯一の担当者が夏期休暇中で対応できない。
人事担当者が不在で、社員からの問い合わせに誰も答えられない。
こうした属人化の弊害は、人手不足だったり、少数精鋭を謳う会社ほど顕著です。
でも、これは人が少ないからではなく、「その人しか知らない」体制を放置しているから起きる問題です。
- 最低限のマニュアル整備
- 業務の見える化と共有化
- 一人のスペシャリストより、複数のゼネラリスト育成
こうした工夫を取り入れれば、少人数の会社でも属人化は解消できます。
「誰が休んでも回る体制づくり」は、まさにこれからの働き方改革の土台とも言えるでしょう。
自社から、柔軟な夏期休暇のあり方を発信しよう
「うちの会社はこうだから」と思い込まず、自社から夏期休暇の分散取得を進めてみませんか?
まずは、就業規則を見直すことからでも構いません。
たとえば「夏期休暇は7月~9月の間に各自で取得可能」と明記するだけで、ぐっと自由度は上がります。
そして何より大事なのは、経営者や管理職が率先して実践すること。
「上が変われば、社風が変わる」。これは休み方にも当てはまります。
社員一人ひとりが「混雑を避けて休める」「家庭の都合に合わせて休める」そんな職場づくりこそ、企業の信頼性を高め、従業員満足度を押し上げる鍵になります。
一斉に休む時代から、自分のペースで休める時代へ。
働き方も、休み方も、もっと柔軟に。