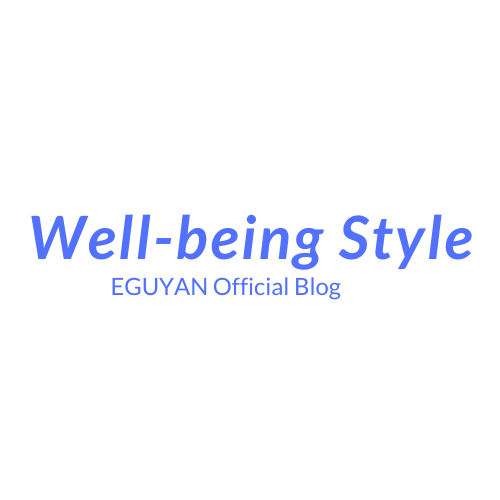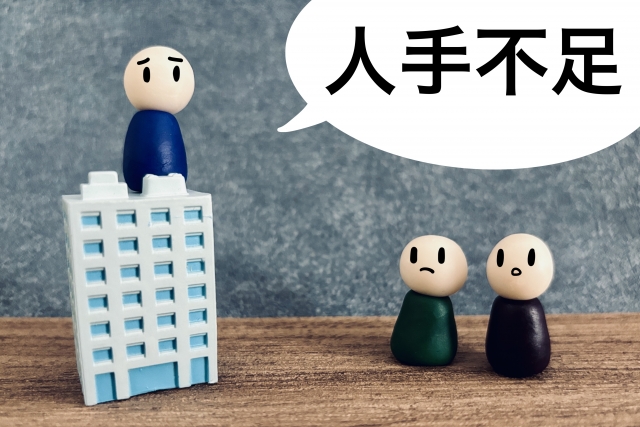継承したいものと、しなくていいもの

すべてを受け継ぐ必要はない。日本には継承すべき素晴らしいものがある一方、今の時代には合わない価値観や仕組みもあります。
継承したい、日本の良き文化と風景
日本には、時代を超えて大切にしたい文化や風景が数多く残されています。
古民家や町屋、神社仏閣といった建築物、地域に根づいた祭りや年中行事、伝統的な食文化、そして自然と共生する暮らしの知恵。こうしたものは、単に「古い」から価値があるのではなく、そこに「人の営みの積み重ね」が見えるからこそ継承すべき対象なのです。
地域の歴史や文化を守ることは、その土地に生きる人たちの誇りを育み、コミュニティの結束にもつながります。
さらに、訪れる人々にとっても魅力的な体験となり、観光や地域活性化の源にもなり得ます。
もう継承しなくていい「古き悪しき」もの
一方で、過去に有効だったものが、今の時代にとっては足かせになるケースもあります。
たとえば、年功序列や終身雇用といった日本型雇用慣行、無意味な上下関係、長時間労働を美徳とする風潮、休暇取得への罪悪感などは、かつての高度経済成長期には必要だったかもしれませんが、現在の価値観や働き方には合いません。
また、会議のための会議や、紙文化の温存、上司への忖度ばかりが優先される組織風土など、時代に取り残された習慣が、組織の成長や個人の挑戦を妨げている現実がまだあります。
こうした「古き悪しきもの」は、いつまでも残していても、誰のためにもなりません。むしろ、時代の流れに合わせて見直し、刷新するべきです。
継承することは尊いが、それは「過去をそのまま再現すること」ではありません。
必要なのは、「今の時代に合った形にアップデートする」ことです。
「何を残し、何を手放すか」の選択が未来をつくる
これからの時代に求められるのは、「すべてを引き継ぐ」のではなく「選び取って残す」という姿勢です。
残すべきものは、形としての文化財だけではなく、人の手によって受け継がれてきた技術や価値観、地域への想いなど、本質的な部分に目を向ける必要があります。
一方で、「惰性で残っているだけ」の制度やルール、時代錯誤の常識は、見直しましょう。
何を捨て、何を活かすか。その判断が、未来の社会を左右していきます。
捨てるにしてもそれを恐れず、大切なものを見極めながら、次の世代へとつないでいきたいものです。