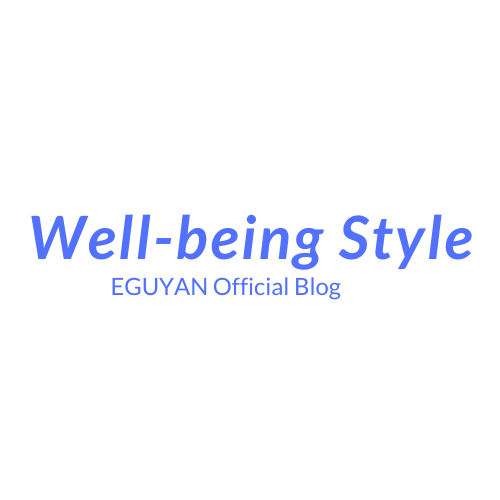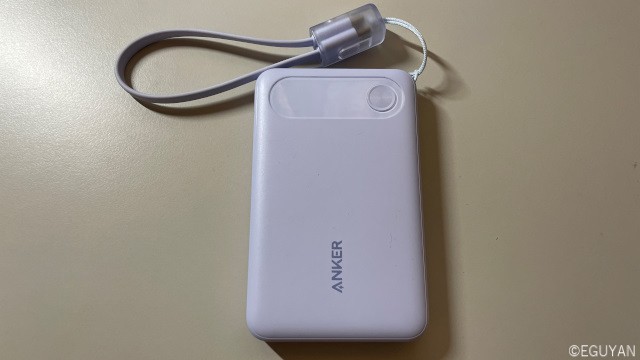お盆ってなんやかんや日本のよき伝統だと思う

明日からお盆、という人は多いのではないでしょうか。
全国的には8月13日から16日が一般的なお盆ですが、地域によって日程はさまざまです。
この時期になると、街の空気や人々の動きに独特のゆったり感が漂い、「ああ、日本の夏だな」と感じます。
地域ごとに違うお盆の時期
多くの地域では8月中旬が定番ですが、沖縄や奄美などでは旧暦の7月15日がお盆にあたり、旧暦なので年によって日程が変わります。
時には9月にずれ込むこともあります。
Wikipediaで調べてみると、東京では新暦の7月15日(もしくはその前後の土日)がお盆というところもあり、同じく根室、函館、横浜、静岡、鶴岡、金沢(一部地域)などもその日程にあたるそうです。
地域や文化によって、同じ「お盆」でもこんなに違いがあるのは面白いものです。
働く人にとってのお盆ウィーク
前職では、お盆ウィークは基本的に休みでした。
もっとも、後半が週明けにかかると休みではなかったかもしれません。製造業にいたときも同じで、理由は「取引先が休みだから」というのが大きかったです。
ただ、前職の場合はそれに加えて「社長が休みたいから」というシンプルな理由もありましたが。
とはいえ、人事や総務の仕事は月半ばにやることが多く、完全に休めるわけでもありません。
結局、1日か2日は出社して、代休を後日しっかり取る…という流れでした。
昔は会社の夏期休暇といえばほとんどがお盆前後でしたが、最近は時期を分散して取る会社も増えています。
お盆の空気と「みんな一斉休み」の意味
今では「好きな時期に休める」制度も増えましたが、それでもお盆ウィークは休む人が多いです。
個人的には、正直、お盆に出社するのはあまりうれしくはありませんでした。
通勤電車が空いていて快適、という声もありますが、心のどこかで「休んでいる人がうらやましい」と感じることもありました。
とはいえ、結局のところ、決まった時期に全員が一斉に休む必要はないと思います。
それでも、お盆という期間が日本の夏の一つの節目として残っているのは、やはり文化的にも人の心の中にも根付いているからでしょう。
なんやかんや言って、お盆は日本の「よき伝統」です。
都会の喧騒が少し和らぎ、帰省や墓参りで家族や故郷と向き合う。
そんな時間が年に一度あるのは、現代の忙しい生活の中で貴重なことだと感じます。