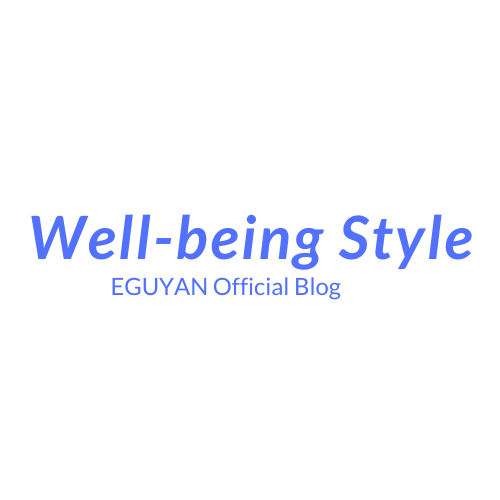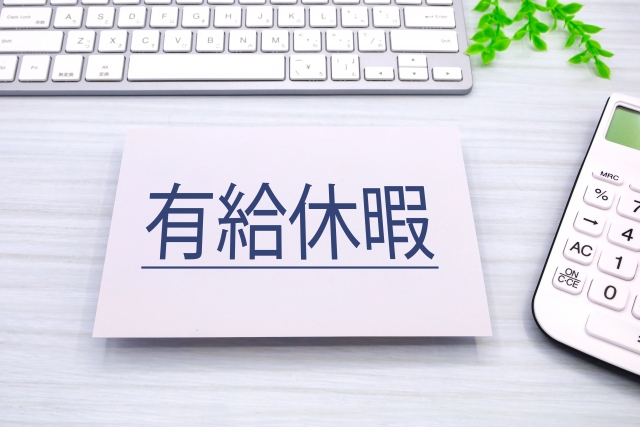オフィスの物理的環境とウェルビーイング

社員のウェルビーイングを考えるとき、制度や働き方だけでなく、「物理的な環境」も無視できません。オフィスの空間設計が誰のためのものかを見誤ると、その環境はむしろストレスの温床になってしまいます。
見た目重視のエントランスと、社員に配慮のない執務空間
私が以前勤めていた会社では、業界柄なのか、社長がとにかく派手好きで、オフィスのエントランスはまるで銀座の高級クラブのような空間でした。お初のお客さんはほぼ全員驚き、確かにインパクトはありましたが、そこを通り過ぎると一転。社員の執務エリアは無機質で、飾り気も工夫も一切ない、機能性だけを追求した味気ない空間でした。
それが昭和から平成に至るまでの、どこにでもある執務空間だったわけですが・・・
執務室の一角には、カウンターバー風のスペース。ここの社長の好みが詰まったスペースで、冷蔵庫だけでなくダーツ機器などが設置されていました。しかし、ほとんど活用されていませんでした。形だけの「福利厚生空間」となっており、社員のリフレッシュにはあまりつながっていなかったのが現実です。
唯一、私たち人事・総務部門が導入した100円で買えるお菓子や飲み物の自販機は、日常的に社員に利用されていました。小さな取り組みではありましたが、「社員のため」の視点から設けた仕組みとしては、社内でも数少ない実用的な工夫でした。
働きたくなるオフィスは“自由”を提供する
退職後、その会社はオフィスを移転し、健保から表彰されるほどの「健康志向」をテーマ(?)にしたアイテムがいくつか導入されたと、会社のホームページで知りました。そうした設備も確かに価値がありますが、それだけでは社員の心身の健やかさは担保できません。
本当に求められるのは、「働きたくなる空間」であることです。たとえば、フリーアドレスでその日の気分や仕事内容に合わせて場所を選べる、少人数ミーティングに適したテーブルが点在している、仮眠やリラックスができる静かなスペースがある――そんな自由度の高い空間こそが、現代のオフィスに必要な設計です。
前職ではすべての社員がデスクトップPCを使っていたため、物理的な場所の移動は不可能でした。さらに、私はイヤな上司のすぐ隣席だったので、日々の業務が心理的に非常に苦痛なものとなっていました。物理的環境が心理的安全性にも影響することは、明らかです。
ガラス張りの社長室がもたらす無言のプレッシャー
社長室は執務スペースのすぐ隣(しかも我々のすぐ隣)にあり、通常は中の様子がガラス越しに見えるようになっていました。しかし、スイッチ一つで瞬時にガラスが曇り、内部が見えなくなる仕様になっていたのです。
この「見えたり、見えなかったりする空間」は、社員にとって想像以上のプレッシャーを与えます。誰が来ているのか、何の話がされているのか、何が起きているのかがわからない状況が、業務中にも無意識の緊張感を生んでいました。空間の設計ひとつで、社員の集中力や安心感がこれほど左右されるのです。
社員のウェルビーイングを高めるためには、制度設計や働き方の見直しだけでなく、オフィスの空間そのものにも意識を向ける必要があります。空間は経営からのメッセージであり、「あなたを大切にしている」という意志が伝わる設計になっているかが問われます。
物理的環境はコストではなく、投資です。社員が「ここで働きたい」と思える空間こそが、企業の生産性と持続性を高める基盤となります。空間のあり方そのものが、経営の質を映し出しているのです。