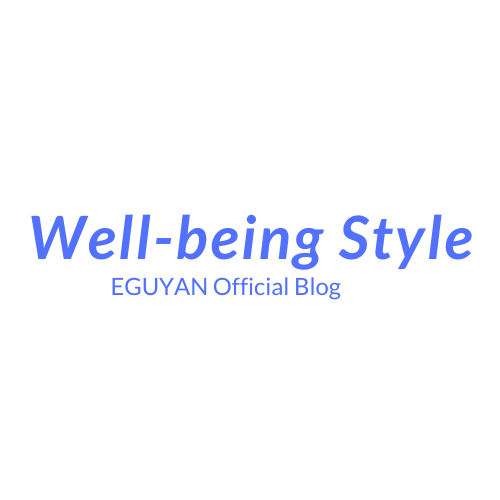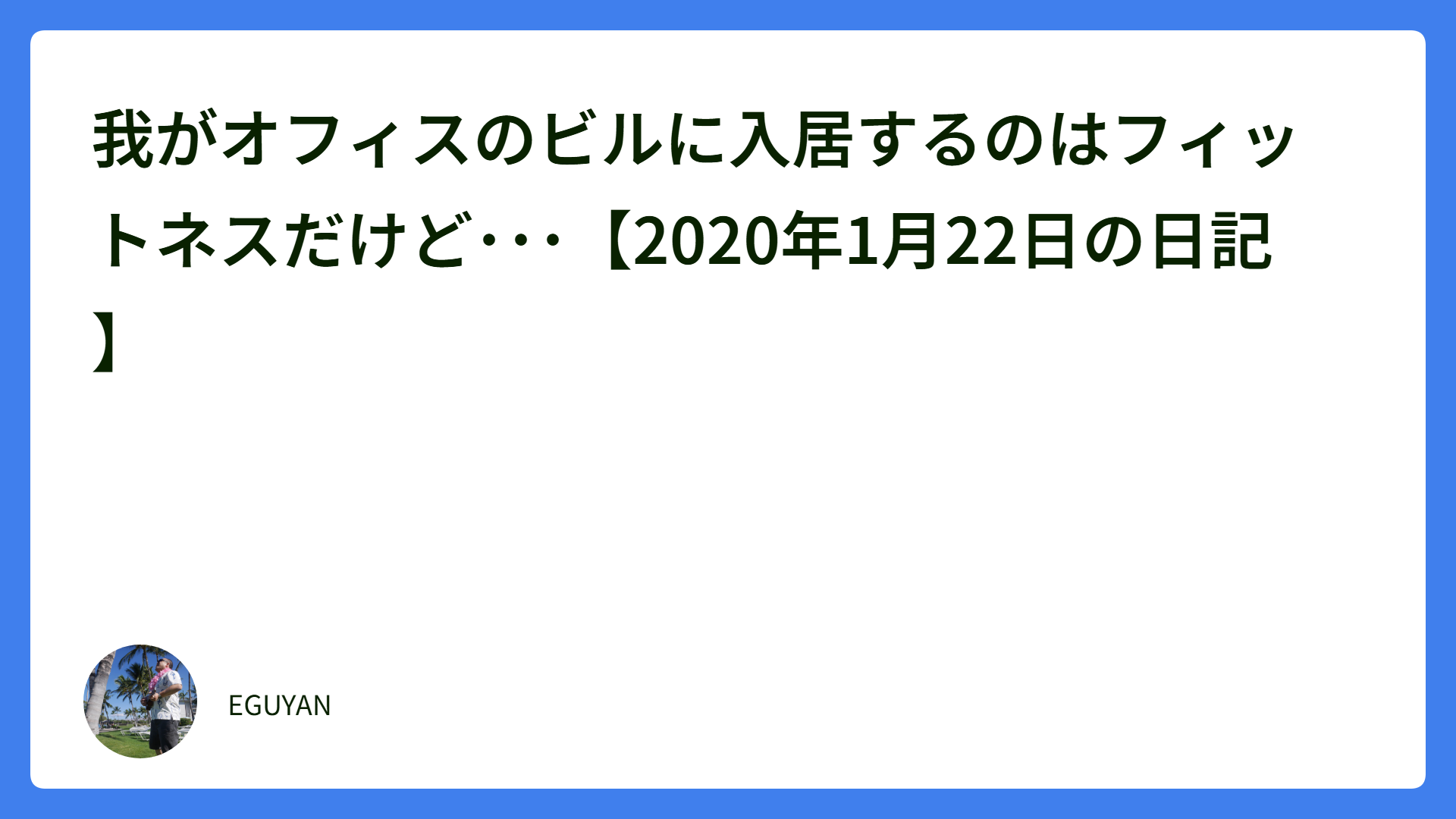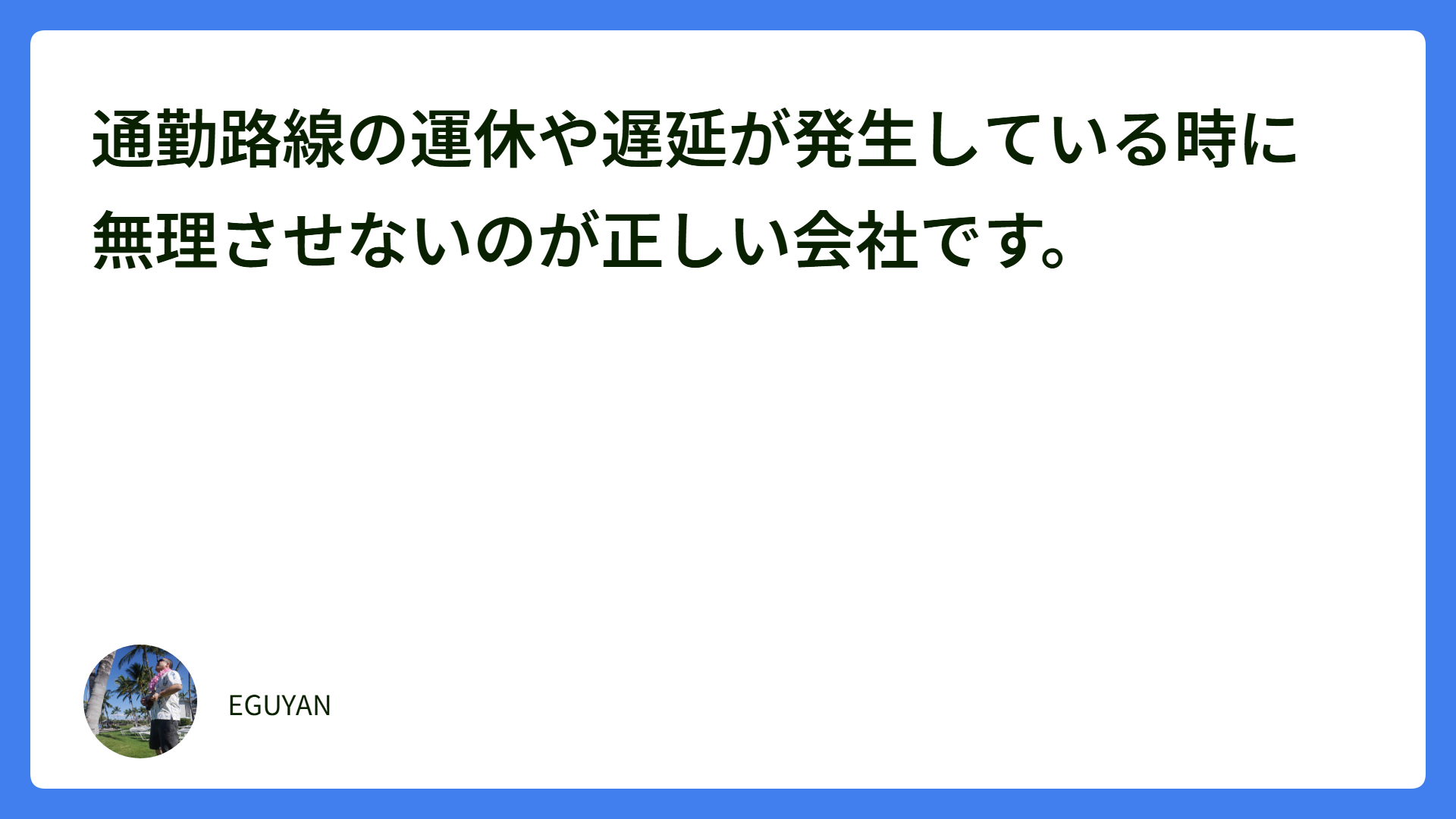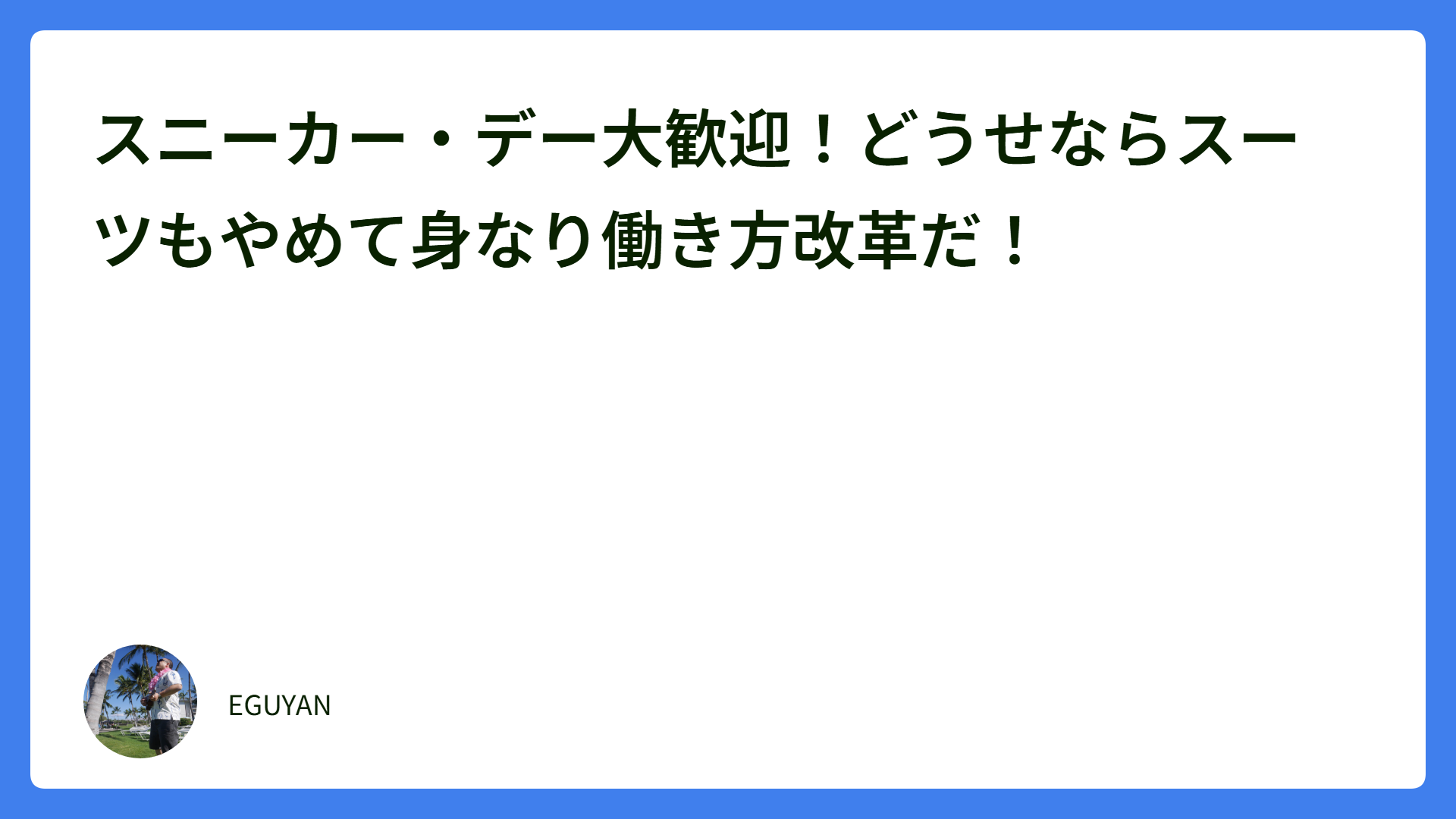マニュアルづくりよりもポリシー(方針)をしっかり決めておく
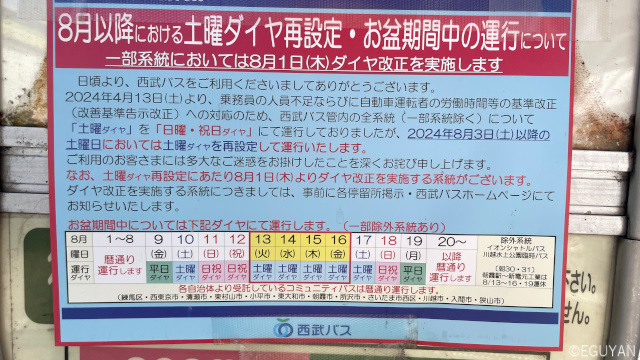
仕事でもプライベートでも、マニュアル通りにいかないことが日常茶飯事です。だからこそ、判断軸となる「方針」を定めておくことが大事です。
マニュアルは標準化には有効。でも限界もある
学生時代、私はファミリーレストランで調理のアルバイトをしていました。そこでは、焼き時間、調味料の分量、盛りつけ位置にいたるまで、すべて細かくマニュアル化されていました。どの店舗でも同じ味と見た目になるよう設計されており、手順さえ守れば誰でも一定の品質を提供できる仕組みです。
こうした標準化が求められる現場では、マニュアルは非常に有効です。生産性も高く、属人化も防げます。新人でも即戦力として動けるようになり、企業としての再現性も担保されます。
ただし、マニュアルには「想定されたこと」しか書かれていません。現実の職場では、マニュアル外の出来事が次々に起こります。
想定外への対応に必要なのは「判断の軸」
人事や顧客対応の現場では、「こういう場合はどうするのか?」という問いに対して、マニュアルでは答えきれないケースが多々あります。条件が少し違っていたり、複数の要素が絡んでいたりすると、マニュアルだけでは対処できません。
そうなると、現場の社員は「マニュアルに載っていないので対応できません」と手を止めてしまうことがあります。これは非常に危険です。現場が“考えること”をやめてしまうからです。
このようなときに有効なのが、「方針(ポリシー)」です。
たとえば、「お客様に安心を与えることを最優先にする」という方針が社内に浸透していれば、マニュアルに載っていない事態でも、自分で判断して行動できます。「正解」よりも、「何を大切にするか」という軸が、現場での意思決定を支えてくれます。
これは、働き方改革の視点からも重要な考え方です。柔軟で自律的な働き方を実現するには、指示待ちではなく、判断できる人材が増えることが不可欠です。
方針に沿った経験が、組織を強くする
方針をもとに実際に行動してみることで、「うまくいったこと」「改善すべきこと」が明確になります。それをチームで共有し、次に活かす。このサイクルが、柔軟に動ける組織文化を育てていきます。
たとえば、ある対応で「こう伝えたらお客様が安心してくれた」「この判断は相手に誤解を与えた」といった具体的なフィードバックをもとに、方針を微調整していく。その過程で、社員の判断力も確実に育っていきます。
重要なのは、「まずマニュアルを作る」ことではなく、「何を大切にして行動すべきか」という方針を明文化して共有することです。そこが定まっていれば、多少のイレギュラーも柔軟に対応できますし、メンバーも不安なく動けるようになります。
働き方改革が進む中、個人の裁量を尊重しながらも組織としてブレない判断軸を持つことは、これからの企業運営に欠かせません。