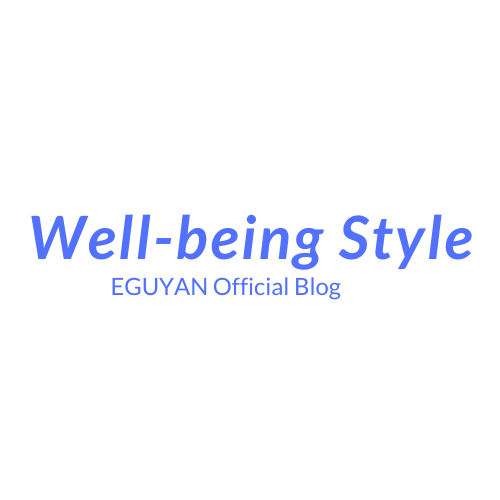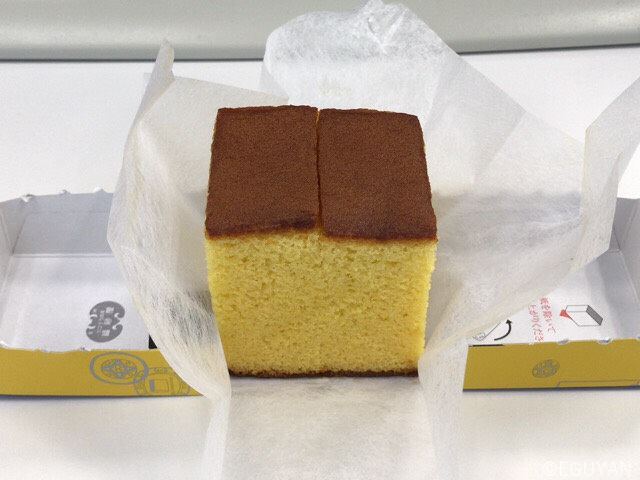転職が前提の時代に、社員エンゲージメントを高める方法

転職が当たり前になった今でも、「自社グループ製品を使うことが愛社精神の証」という空気が残る会社は少なくありません。
けれども、時代に合わないその発想は社員の共感を得にくく、かえって逆効果になることもあります。私自身の経験を通して、その実態を整理してみたいと思います。
業界ごとに違う「自社製品利用」の文化
これまで私は、
・電機
・携帯電話(派遣社員)
・自動車部品(派遣社員)
・自動車(トラック)業界
・海運(三菱系)
といった業界を経験してきました。
携帯電話業界では社員割引があったものの、ドコモ縛りでした。
自動車部品販売店では、派遣社員なのに親会社コラボ車の購入を勧められたこともあります。
トラック業界では、グループ外の車を使う社員は遠くの駐車場に追いやられそうになりましたが、労働組合が抗議して事なきを得ました。
海運会社では、懇親会でキリンビールが必須という暗黙の了解がありました。
電機業界の社販は量販店の方が安いことも多く、ほとんど利用しませんでした。
一方で契約保養所は本当に安く特典も多く、よく使っていました。
こうした事例から「自社製品利用が社員への圧力になりやすい」ということです。
愛社精神は購買で測れない
転職が主流になった現代において、会社への忠誠心を「自社製品を買ったかどうか」で測るのは無理があります。
社員はキャリアの節目ごとに所属が変わります。
だからこそ、強制的な利用や暗黙の了解に依存した“忠誠心”は長続きしません。
むしろ不公平感やモチベーション低下につながり、離職リスクを高めます。
本当に必要なのは「社員が自由に選んだ結果、自社製品を自然に使いたくなる状態」をつくることです。
納得できる価格やサービス、そして安心して使える体験があってこそ、社員は誇りを持って自社製品を選びます。
これからの企業に必要な考え方
企業が大切にすべきは、社員に購入を(心理的な部分を含め)強いることではなく、選ばれる理由を提供し続けることです。
たとえば社販では単なる値引きではなく、保証延長や修理の優先対応といった「付加価値」で納得感を高めることができます。
競合製品の使用を禁じるのではなく、比較やフィードバックを製品改善に活かす文化を持つことも重要です。
また、福利厚生や懇親会などで特定の製品に縛るのではなく、公平性を重視することで心理的安全性が守られます。
愛社精神は無理に示させるものではありません。
社員が「自然に使いたい」と思える製品やサービスを提供することが、結果的にブランド価値を高め、エンゲージメントを強くしていくのです。