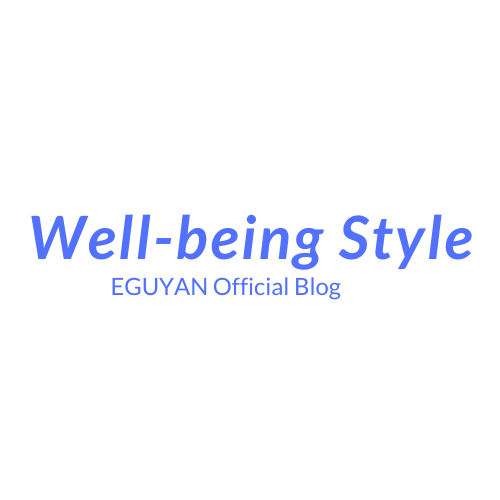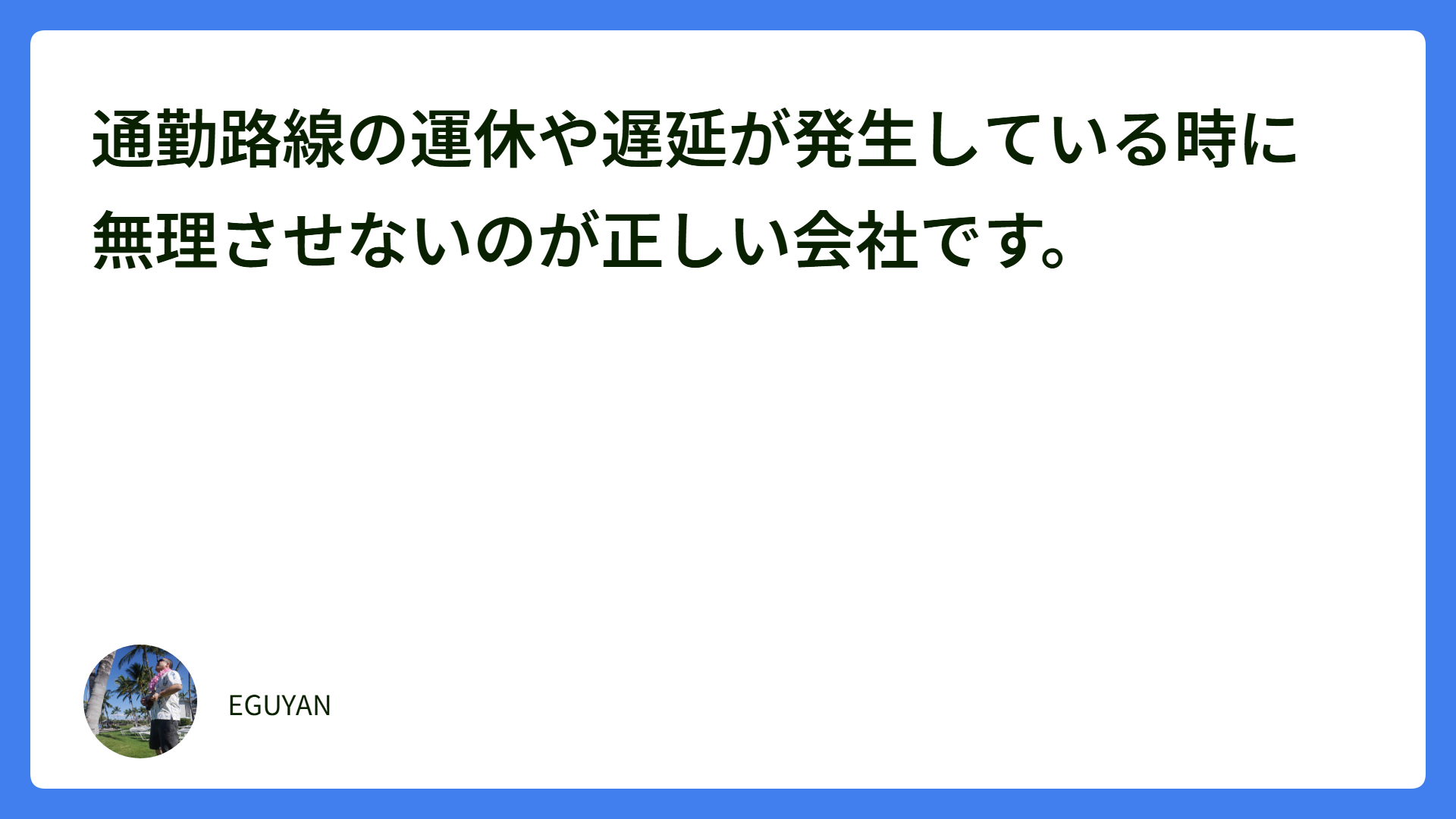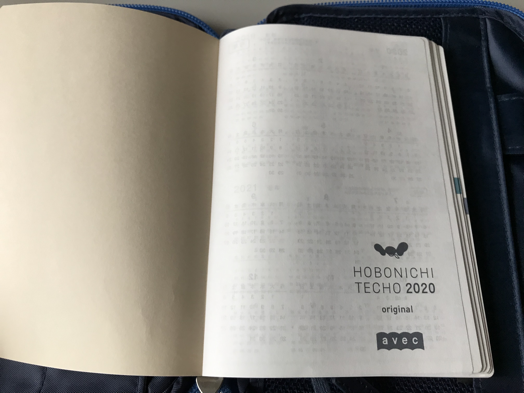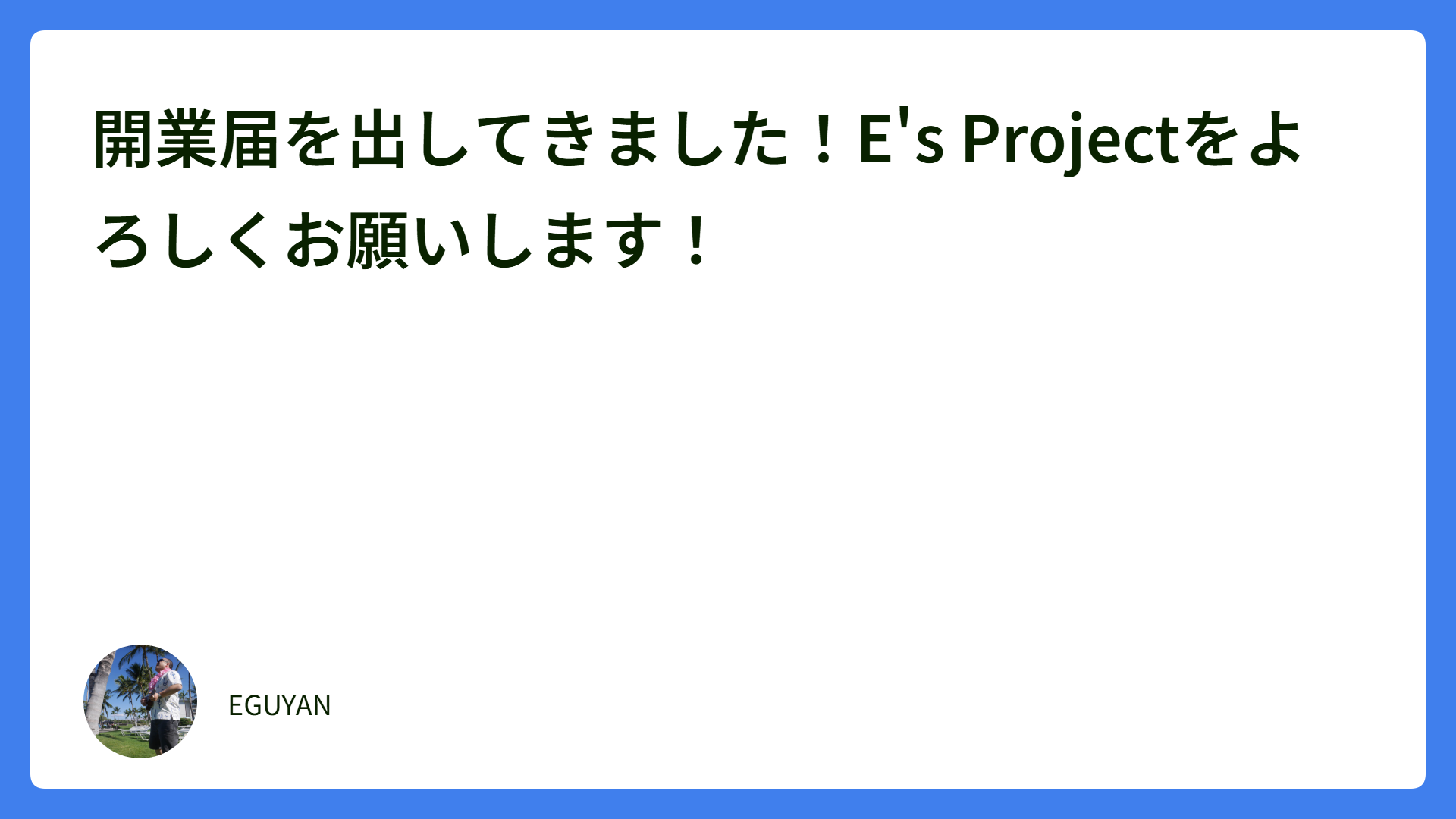一方的な転勤辞令、いい加減廃止すべき

ある日突然、引っ越しを伴う遠方への転勤命令。
それがキャリアのチャンスと捉えられる人もいれば、家庭や介護など事情を抱える人にとっては人生を左右する「通告」になることもあります。
転勤制度の建前と、現場が受ける実害
私自身は、これまで引っ越しを伴う転勤は経験していません。
首都圏内での異動はあったものの、社会人になった当初から「一方的な転勤命令」に対して疑問しか感じてきませんでした。
企業が転勤制度を正当化する理由としてよく挙げるのが、「人材育成」「不正防止」「適材適所」です。
しかし、果たして本当にそれが理由なのでしょうか?
たとえば「人材育成」が目的なら、なぜ本人の意向が無視されるのでしょう。
「適材適所」なら、転勤によって環境が激変し、モチベーションが下がる可能性はどう考えているのでしょうか?
制度の大義名分と、現場が受けるダメージには大きなギャップがあります。
特に引っ越しを伴う転勤となれば、配偶者のキャリアや子どもの教育、親の介護など、家庭全体への影響は甚大です。
介護中の社員に転勤命令、その末路は…
2024年7月の朝日新聞(asahi.com)に、象徴的な事例が掲載されていました。
母親を介護していた社員に対し、会社が突然北海道への転勤を命じたのです。
その方は何度も断り続けましたが、人事や上司からは「拒否すれば懲戒解雇の可能性がある」と圧力をかけられたといいます。
最終的には命令が白紙になりましたが、おそらく会社の顧問弁護士から「訴訟になれば会社が不利になる」と指摘されたのでしょう。
このケースは、転勤制度が社員個人の生活や人生をいかに無視してきたかを象徴しています。
配慮のない転勤命令が、どれだけ信頼関係を損ない、企業リスクにつながるか、改めて考えさせられます。
実際、「エン・ジャパン」が2025年3月に行った調査では、転勤経験者のうち4割以上が、転勤をきっかけに退職を考えたと回答しています。
人材確保が課題となる今の時代に、転勤制度そのものが「離職リスク」になっているのです。
「会社のための転勤」から「自分と家族のための選択」へ
昔ながらの企業文化では、「会社の命令は絶対」という価値観が根強く残っています。
しかし、令和の今、働く人の価値観は変わりました。
自ら希望して転勤するのなら良いですが、望まない転勤によって家庭が崩れたり、親の介護が立ち行かなくなったりしても、会社がその責任を取ってくれるわけではありません。
社員の人生は会社のものではなく、個人とその家族のものです。
これからの時代、企業には「転勤制度の廃止」または「本人の同意があった場合のみの運用」が求められます。
人事制度をアップデートし、「社員が働き続けられる会社」を目指す。
その第一歩として、「一方的な転勤命令」に終止符を打つことが必要ではないでしょうか。