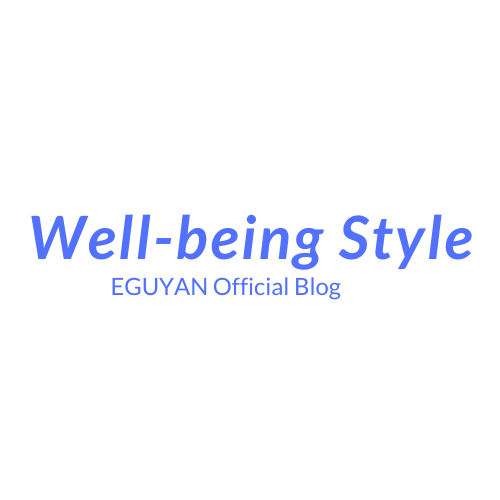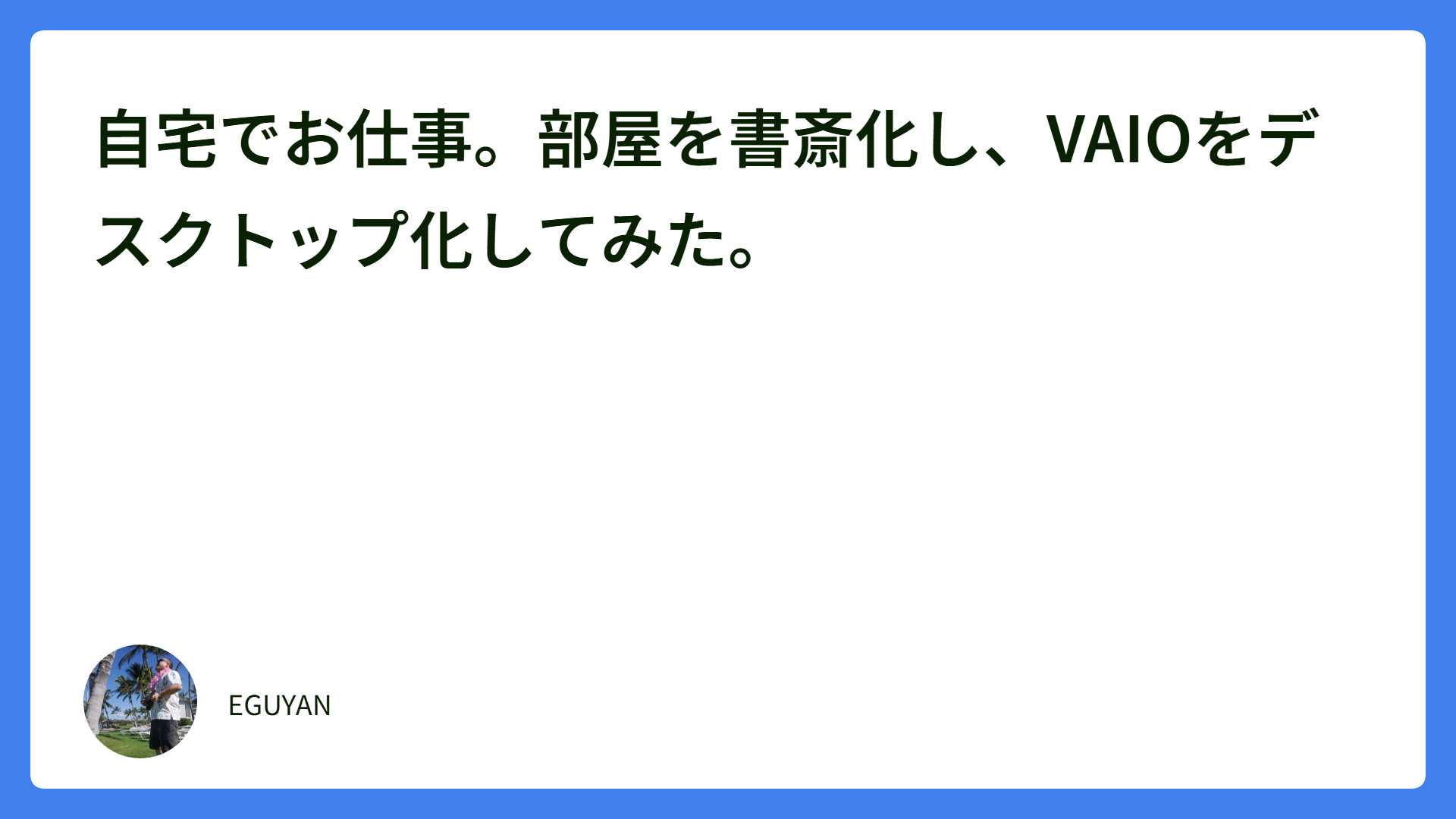リコールはできるだけ避けたいが仕方ない。発生したときの対処法を考えておく
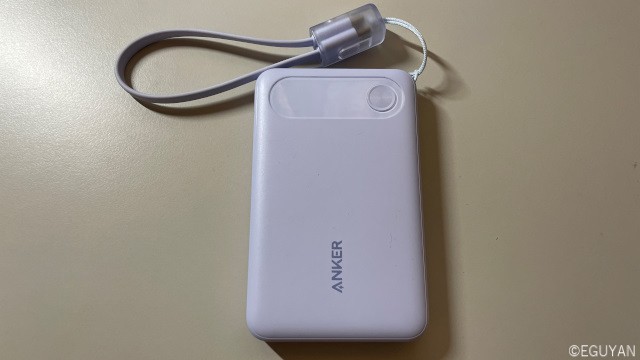
どれだけ注意していても、ミスは起こることがあります。できれば避けたいリコール。けれど、万が一のときに備えて、事前に備えておくことが大切です。
リコールは初動がカギ。発覚したらすぐ対処する
この度、初めてリコールを経験しました。
2月に購入したモバイルバッテリーです。
沖縄に行く際、家から普段使っているモバイルバッテリーを忘れてしまったため、取り急ぎ羽田空港第3ターミナルに隣接する羽田エアポートガーデンのAnkerのショップで購入しました。
その場しのぎ的でいいやと思っていたのですが、せっかく買うなら無名メーカーのは避けたかったし、たまたまAnkerのショップがあったので(逆に言えば他になかった・・・)。
購入した機種が、最近になってリコール対象と知り、手続きをしました。
今は当該機種の送付用キットを待っているところ。
リコールを望む人はいません。組織の中で働く人も、個人で仕事をしている人も、ミスをしないよう最大限の注意を払っているはずです。それでも、人は誰しもミスをしてしまうものです。
問題は、発覚後にどう動くかです。ミスを放置したまま進んでしまえば、重大な事故や損害につながり、企業や個人の信頼を大きく損なうおそれがあります。
だからこそ、リコールの兆しを感じた段階で迅速に対応することが重要です。会社であれば、ただちに上司や関係部門に報告し、指示を仰ぐ。個人事業主であれば、状況を整理し、顧客への説明と対応策をスピーディーに準備することになります。
働き方改革が進み、個々の判断や行動力が求められる今の時代においては、現場での気づきと素早い対応が、組織の信頼性を支える力となります。社員が安心して報告できる風土があること、それがウェルビーイングな職場づくりにも直結します。
マニュアルとポリシーの両方を整えておく
リコールが必要になったときに求められるのは、誠実さとスピード、そして準備です。まずは真摯に謝罪し、状況を正確に伝える。そして、代替案や補償、再発防止策を具体的に示すことが信頼回復への近道になります。
このような場面では、あらかじめ一定の対応マニュアルを作成しておくことが有効です。「こうなったら返金」「この場合は交換対応」など、冷静に判断するための基準を持っておくことで、迷わず動けます。
加えて、マニュアルに加えて「自社としてどこまで責任を持つか」というポリシーも設定しておくと、より柔軟かつ一貫した対応が可能になります。たとえば、キャンセルポリシーのように、逆にこちらから補償の方針を明確にしておくような設計です。
このようなルールと姿勢が社内に浸透していれば、従業員は自信を持って対応でき、心理的安全性も高まります。結果として、職場全体のウェルビーイング向上にもつながります。
一人でも冷静に動ける力を持つ
リモートワーク、副業、個人事業など、「一人で判断する働き方」が当たり前になりつつあります。こうした環境では、自分以外にミスに気づいてくれる人がいないことも少なくありません。
ミスに気づいたときは、まず深呼吸して冷静になることが大切です。もちろん、焦ります。心臓はバクバク、頭は真っ白になるでしょう。
でも、焦りから感情的な行動をとると、かえって状況を悪化させる可能性があります。事実関係を整理し、顧客や関係者に誠実に伝え、修正・補償などの具体策をすみやかに講じます。
一人で仕事をするということは、すべての責任が自分にあるということです。同時に、それは信頼もすべて自分の行動で積み上げられるということでもあります。自分の対応力こそが、ビジネスの持続可能性を左右します。
信頼を失わないために必要なのは、日頃からの備えと、いざというときの冷静さです。